東京が滅んだら、音楽の首都は札幌に移ればいい。サカナクション「834.194」
ストーリーの時代の申し子になってしまった
2013年ごろに使われていた(ような)「付加価値」という概念は、今ではそれ自体に付加価値を加えて「ストーリー」という概念で消費をされるようになった。
札幌と東京、直線距離で800km以上ある二つの大都市で感じたことー札幌に対する郷愁と東京で向かい合った複雑な想いーをコンセプトに、バンドの軌跡を示したような2枚組。ストーリー性を持たせたことを包み隠さず、むしろ一層押し出した作品が2019年に出たことは偶然だろうか。
望郷からはじまる東京の音
シングルでリリースされる楽曲はダサい部分が5%くらい必ずある。これはJ-POPであることを示すためのアレンジであると認識していたが、そろそろ(と言って5年以上経ったが)アルバム曲の洗練された音を聴きたくて仕方なかった。その願望を1枚目1曲目「忘れられないの」がいきなり叶えてくれた。
願いを叶えただけでなく、アルバムの提示する価値観、ともすればバンドが最初から語っている価値観を1曲目にして80%以上提示してきた。この価値観は、後半そして終盤で更に展開される。
続いて「マッチとピーナッツ」は、懐かしいJ-POPの匂いがするサウンドにのせてオルタナティブな歌がテンポ良く流れる。すごく懐かしい感じがするんだけど、これが何なのかは未だ分からない…。
1枚目3曲目からは「陽炎」、「多分、風。」、「新宝島」と、アップチューンのシングル曲が続く。ベスト盤も尻尾を巻いて逃げ出すような並びであるが、不思議とおさまりが良い。絶妙なバランスで成り立っているが、1枚目の世界観を表現するためにはこの並びでなければならないと気付くのは2枚目に入ってからだ。
ダサい部分を5%どころか50%ぐらい出してきてずっこけてしまったのは「モス」。いや、ほんまにいつの時代の曲やねん、と苦笑いしていた。歌詞はその古風なサウンドと対照的に、バンドの最近の(NFを始めた頃からだろうか)価値観を示してくる。結構計算高いな。
「聴きたかったダンスミュージック、リキッドルームに」、「ユリイカ(Shotaro Aoyama Remix)」、「セプテンバー ー東京 versionー」は組曲のように連なっている。東京で感じてきたことがヒリヒリと肌を刺す。決して明るいわけでも希望があるわけでもない。かと言って、絶望して自暴自棄になっているのとは違う。
あの土地にいるからこそ洗練された音楽が、少しずつ故郷へと戻っていく。得たものを捨てることなく、故郷を出た頃とは違う持ち物を抱えながら。そのような光景が浮かび、胸が苦しくなる。
東京からはじまる、望郷の音
2枚目1曲目の「グッドバイ」。安直な発想では東京と別れを告げる、といったところだろうか。それは雑だとしても、ここがアルバムの分水嶺となり、シングル曲の並びも別れや苦しみ、望郷などやや後ろ向きなテーマのものが並ぶ。歌詞カードのアートワークがガラッと変わるのも印象的だ。
「蓮の花」、「ユリイカ」とこちらもシングル曲が並ぶが、1枚目の三連続とは全く意味合いが違う。感じられたのは、迷いや戸惑いだった。
「ナイロンの糸」は、もっとはっきりと迷い、戸惑いを示す。それに加え、後悔も歌う。中盤で入ってくる管の音が船の汽笛のように寂しく響く。
蝉時雨をバックに歌われる「茶柱」は、この作品での底だろう。もはや後悔しか歌われず、それを縁起物であるはずの茶柱をテーマにしているのだ。
底まで落ちたらあとは上がるしかない。「ワンダーランド」は明るいサウンドが程よいビートで進行していく。バンドサウンドを前面に出した曲は久しぶりで、初期〜中期の作風を彷彿させる。数曲ぶりに前向きな歌詞が歌われる。が、それも最後にはノイズに飲み込まれ、ひと時の希望だったと感じさせる。
「さよならはエモーション」は、前曲で示された世界から現実に戻ってきた感覚が強く、何度も聴いたはずの曲なのに全く異なって聴こえる。胸に迫るものがより強い。
アルバムの核となるインスト曲「834.194」。どうジャンルをつければいいか分からないが、ジャケットのイメージと結びつくサウンド、音のうねりを包むように優しく重なり合う様々な音。変化に富みながら時おり覗かせるある音が、どういうわけか距離や時間などを想起させる。この曲はタイムマシンであり、乗り物なのかもしれない。
アルバムのラストトラック「セプテンバー ー札幌 versionー」。
東京versionと同じ曲なのに、憑き物が落ちたかのように、クリアに聞こえてくる。楽器が少ないとか、マスタリングが違うとかでは(多分)ないのに、東京のそれより丁寧に、はっきり歌われているように聴こえる。
音は確かに変わった。けれど言葉の根底にあるものは変わることがなかった。そんな物語を二つの「セプテンバー」が示している。800km以上の距離と、10年以上の時を経ても。
ストーリーを認め、誘(いざな)ってくれるアルバム
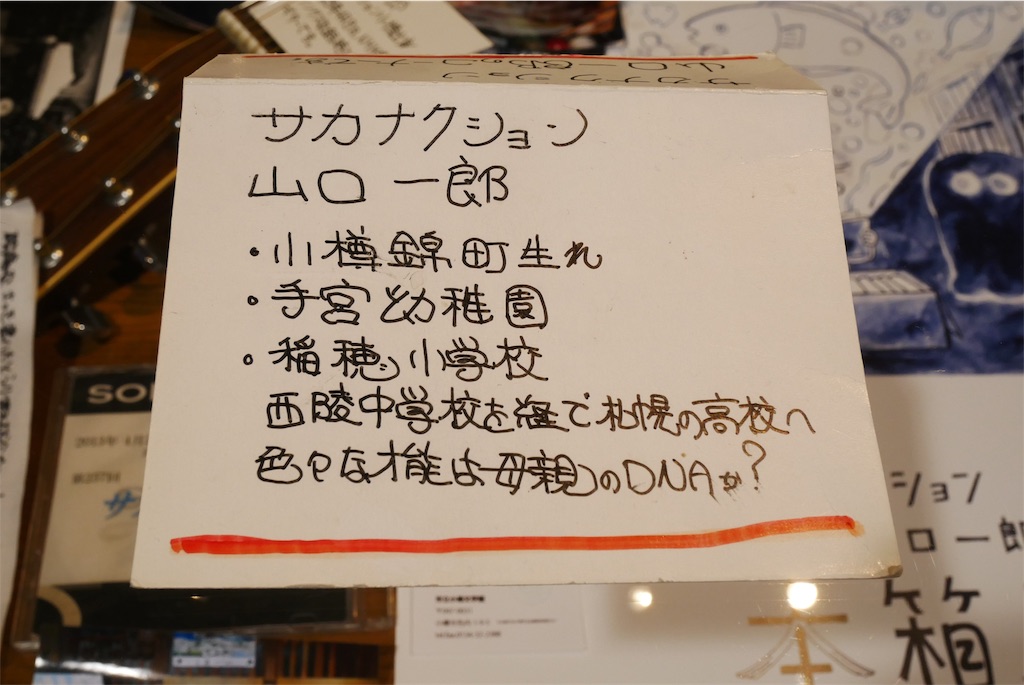

カッコ悪い名前のバンドが出てきたなと思ったのが10年前。
地元を離れる直前、mixiの日記に「ルーキー」の歌詞を引用したのは8年前。
RSRのステージでゴリゴリのアレンジをしてオーディエンスを置いてけぼりにした光景を見たのが5年前。
NFに行き、ヘロヘロになってリキッドルームを出た時に未だ夜が続いてるのが歌のそれと一緒だなと感動したのが2年前。
自分のストーリーにも重ねたくなるように、それも(オールオッケーとは言ってくれないだろうが)黙認してくれるようなコンセプト。寄り添ってはくれないが、寄ってくる者は拒まない。過去を直視させた上で、それらを肯定してくれるような優しさを感じた。
6年間、待った甲斐があった。